行方不明者がいるときの共有解消
2025/09/20
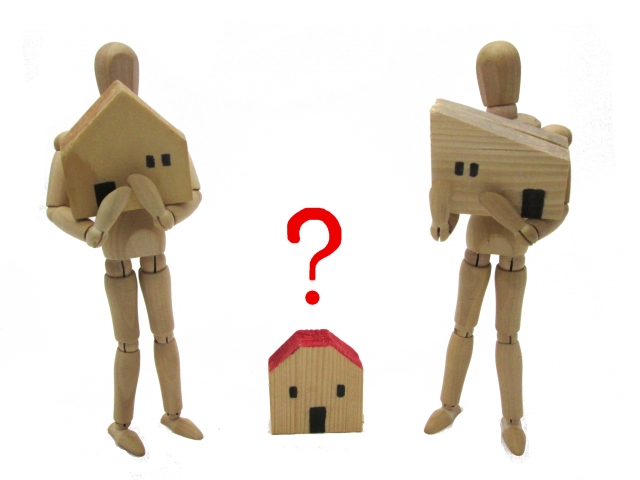
これまでは、共有者全員の連絡が取れる状態であることが前提でしたが、共有でよく耳にするお悩みが「共有者に行方のわからない方がいる」です。
これによく効く民法改正が2023年4月から施工されています。
【ケース①】相続が生した際に相続⼈の中に⾏⽅不明者がいる場合
相続した共有状態の不動産について、①相続開始から10年を経過したときに限り、②地⽅裁判所に申⽴てを行い、その決定を得て、③⾏⽅不明相続⼈の持分の時価相当額の⾦銭を供託した上で、他の共有者は⾏⽅不明相続⼈の持分を取得できることになりました。(改正⺠法262条の2)
共有者が誰なのか確定することで、共有状態の解消に向けた動きをとることができます。
【ケース②】相続登記が完了してから、共有者の中に⾏⽅不明者がでた場合
この場合は、①相続開始から10年を経過したときに限り、②地⽅裁判所に申⽴てを行い、その決定を得て、③⾏⽅不明共有者の持分に応じた時価相当額の⾦銭を供託して、④他の共有者全員は⾏⽅不明共有者の持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡できることになりました。(改正⺠法262条の3)
こちらは、⾏⽅不明者の持分も含めて、不動産全体を売却できるというものです。
【ケース①】の場合でも、他の共有者が⾏⽅不明者の持分を取得した後に、不動産を売却するのは二度手間となるため、【ケース②】と同じ流れで、不動産全体を第三者に譲渡できます。
ちなみに、相続した不動産ではない共有不動産については、10年経過の要件はありません。
共有者の中に行方不明者がいるために「にっちもさっちもいかない」問題に長期間お悩みの方、上記の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
