共有にもちょこっとメリット
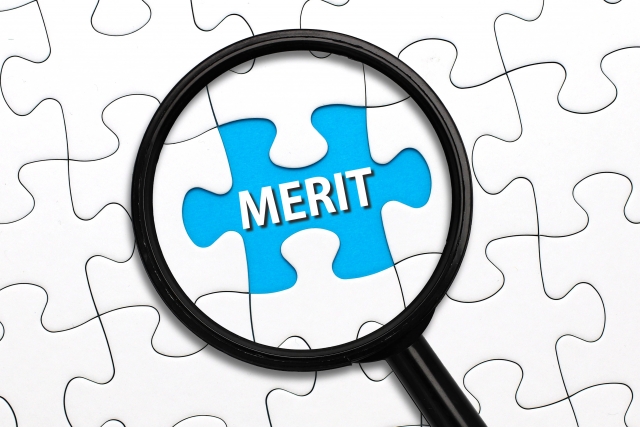
ほとんどの場合、不動産は他の財産と比べて金額が大きく、気軽に売買や譲渡したりすることができません。
なので、とりあえず法定相続分通りに相続して、共有名義にすることはデメリットが大きいと言わざるを得ません。
でも、「相続後早めに」「共有者全員で」「解消する」場合には、メリットもあります。
勝手に呼んで『計画共有』
今回は共有のちょこっとメリットをお話します。
①遺産分割の揉め事は後回し
遺産の分割方法で揉めそうになった際に、一旦の解決策として共有名義にすることで、少し時間をかせぐことができます。
共有名義はいくつかの方法で後から解消できるため、それを前提として共有名義とし、場を収めておくのです。
また、相続した不動産が収益物件で、今後の利益も見込めるようであれば、共有名義のままにして持分ごとの利益を受け取る形で損をせずに済めば、公平とも言えます。ただし、将来的に不公平を感じる結果となってしまう可能性も高いので、共有の期間を長期化させないようにしておく方が無難です。
②売却時の利益に対する税金の控除額が上がる
共有名義でも相続した空き家を売却すると、3,000万円の特別控除は適用されます。
相続⼈が2名の場合:⼀⼈あたり3,000万円まで控除可能(合計6,000万円)。
相続⼈が3名以上の場合:⼀⼈あたり2,000万円まで控除可能(2,000万円×相続人の数)
人数によって一人当たりの控除額が変わりますが、合計すると控除できる総額があがります。
相続した不動産の多くは、新しい物件ではないので建物は減価償却され、土地も元から保有していたパターンが多いため取得費が少なくなり、売却すると譲渡所得税がかかることが多いです。そのため、この控除による効果は極めて大きいと言えるでしょう。
ただし、以下の条件があります。ご注意のほどお願いします。
○共有不動産の売却代⾦は1億円以下(土地と建物の代金は合計されます)
○昭和56年5月31日以前に建築された建物で、区分所有建物登記がされている建物でないこと。(マンションは対象になりません)
○相続開始の⽇の翌⽇から、3年を経過する⽇の属する年の12⽉31⽇までに売却していること。
○相続開始の直前まで被相続⼈が住んでいた家屋であること。(あくまで自宅)
