貸し借りと贈与
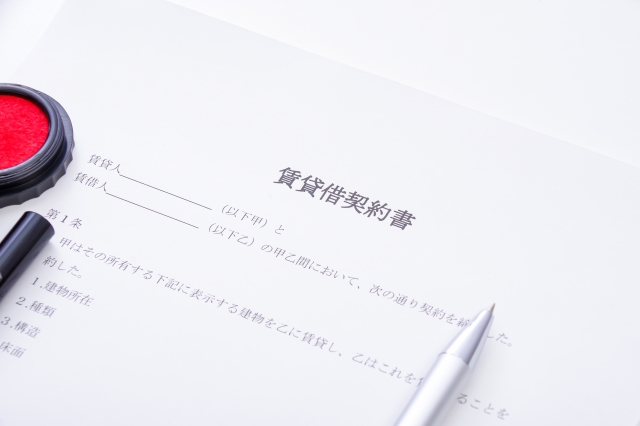
マイホームを購入するときや建てるとき、親御さんが費用の一部を出してくださる。
贈与あるあるです。
親や祖父母から住宅取得資金を援助してもらう場合、非課税で贈与を受けられる特例があることをご存じの方は多いと思います。
でも、非課税で贈与してもらえる金額は、建物の性能に合わせて、1000万円までか、500万円まで、とても取得費用の半分もいきません。
自分の家でしょ。親に買ってもらうの?うらやましすぎる~の、声も聞こえてきそうですが、非課税贈与を超える資金援助をされる親御さんも、ちらっ、といらっしゃいます。
そこで、贈与じゃないよ、貸付だよと言って貸借契約にしたとしても、契約書も交わさずに口約束だけで済ませてしまうと、後になって、税務署から「それは貸借じゃなく贈与じゃないの?」と指摘され、予期せぬ税金問題に発展するケースも少なくありません。
また、仮に金銭消費貸借契約書を作成していたとしても、実際の返済が全く行われていないなど、実態が伴っていなければ、貸付そのものが贈与と判断されて、結局、予期せぬ税金問題に…以下同文です。
そこで、贈与とみなされないための3つの対策です。
①「金銭消費貸借契約書」を作成しましょう
「誰が、誰に、いつ、いくらを貸し、いつまでに、どのような方法で返し、利息はどうするか」といった貸借の条件を具体的に記載し、必ず書面で契約内容を明確にしましょう。
これが、貸借関係を示す証拠となります。
②「適正な利息」を設定し、実際に受け払いしましょう
適正な利息を設定して実際にその支払いが行われることで、単なる資金の移動ではなく、 真実な貸し借りであることを税務署に示すことができます。
③「返済記録」を確実に残しましょう
契約通りに返済が実行されている事実を記録として残すことが大事です。
お勧めなのは、通帳からの振込を利用すること。通帳に「いつ、誰から誰へ、いくら」送金されたかの記録が客観的に残り、返済の事実を明確に証明できます。
税務署から「贈与」とみなされず、貸借関係であることを証明するには、「きちんと返済することを前提とした正式な貸し借りである」ことを客観的な証拠で示すことです。
また、親族間での貸し借りは、贈与税だけでなく、将来発生する「相続税」にも影響します。
貸した方(主に親)が亡くなった場合、その方が有していた親族(主に子)への貸付金も、他の財産と同様に、相続税の課税対象財産として扱われるのです。
相続対策から漏れていた貸付金があると、せっかくの対策が無駄になってしまう可能性もあります。
特に貸付の金額が大きい場合や、返済期間が長い場合、契約内容について少しでも不安がある場合などは、専門家へ相談しましょう。
ここは安全第一で。
